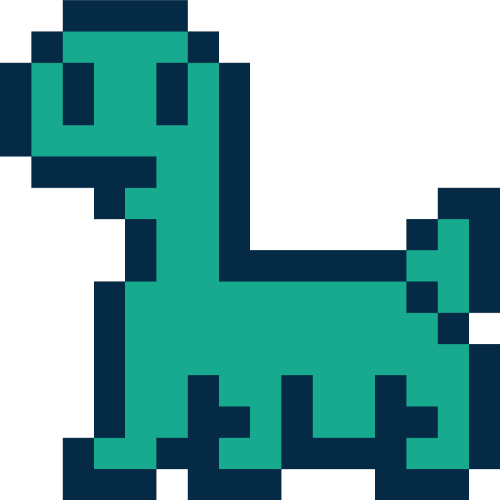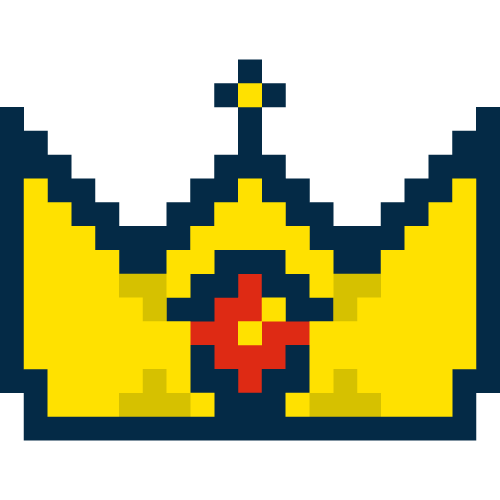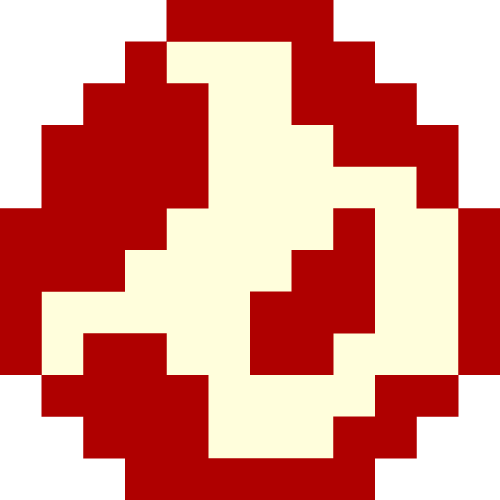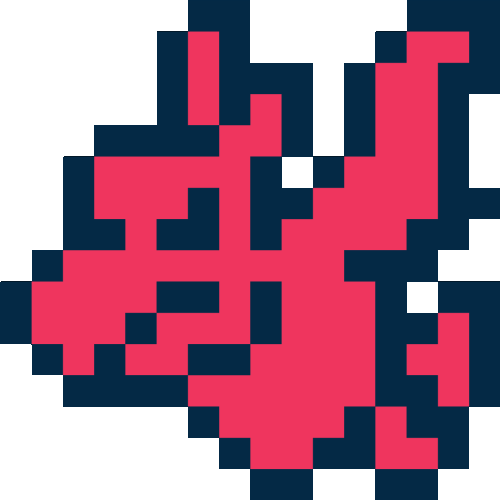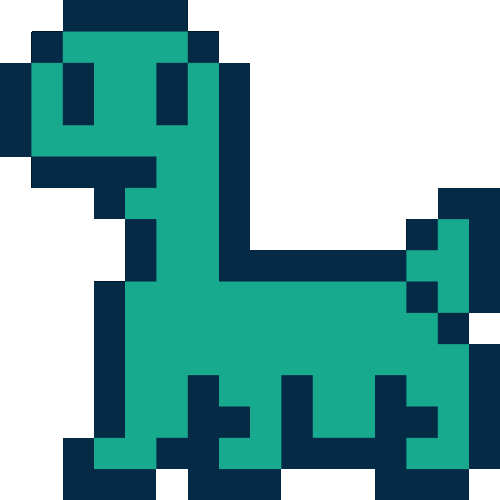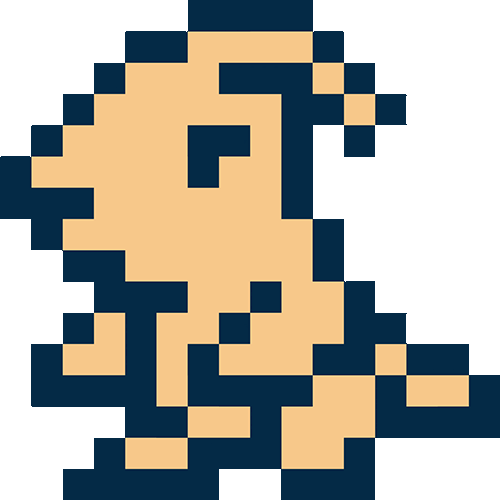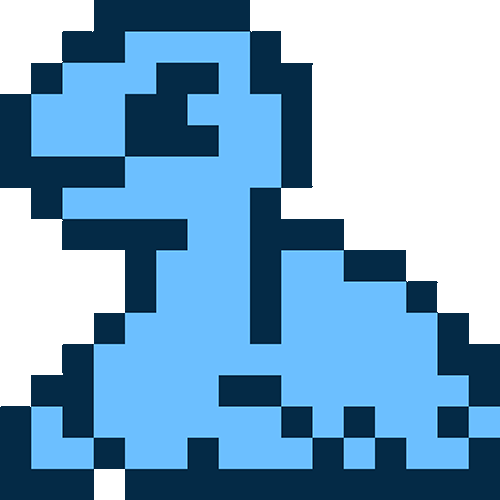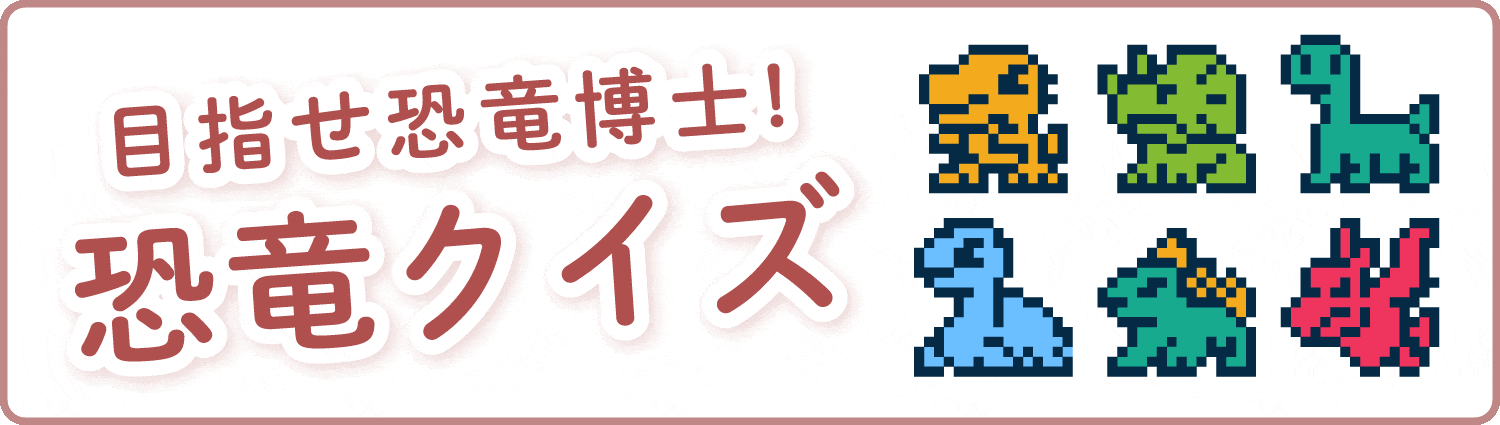恐竜絶滅の真相:チクシュルーブ隕石が招いた「K-Pg境界事件」の全貌

恐竜の絶滅は、地球の歴史上最も劇的な出来事であり、長年にわたり科学の謎とされてきました。
しかし、現在では約6,600万年前に起こった巨大隕石の衝突こそが原因であるという「隕石衝突説」が圧倒的に有力です。

恐竜絶滅の原因は、「隕石衝突説」が圧倒的に有力。
この大災厄は、中生代の白亜紀(K)と新生代の古第三紀(Pg)の境界にあたることから、「K-Pg境界事件」と呼ばれています。
これは、複合的な大災害と長期的な環境激変が連鎖的に発生した、史上最大級の災厄でした。
第1章:隕石衝突を裏付ける決定的証拠とクレーター
隕石衝突説が最も有力とされる根拠は、世界中で発見される地層の「地質学的指紋」と、巨大な衝突痕(クレーター)の存在にあります。
決定的証拠:イリジウムのスパイク
K-Pg境界で堆積した岩石層からは、地球の地殻には極めて少量しか存在しない貴金属のイリジウムや白金族元素が、通常の1000倍以上の高濃度で検出されています。
これらの元素は隕石や小惑星では豊富に含まれており、宇宙から飛来した物質が地球上に降り積もったことを示す決定的な証拠とされています。
また、隕石衝突のすさまじい圧力によって生成される衝撃石英の粒や微小ダイアモンドの存在も、巨大な衝撃波のエネルギーを証明しています。
巨大衝突痕:チクシュルーブ・クレーター
原因を引き起こした小惑星の衝突地点は、現在のメキシコのユカタン半島沖にあるチクシュルーブ・クレーターだと特定されています。
幅約10〜12kmにも及ぶ巨大な小惑星が直撃し、広島型原爆の10億倍とも言われるエネルギーで、直径170kmから200kmに及ぶ巨大なクレーターを形成しました。
第2章:衝突の瞬間:短期的な大災害の連鎖
幅10kmの巨大隕石が地球に直撃した瞬間、地球環境は想像を絶する規模の短期的な大災害に見舞われました。

巨大隕石の衝突が引き起こした短期的な大災害の連鎖
瞬間的な破壊と灼熱の波
衝突の瞬間、巨大な熱放射が発生し、衝突地点の周辺地域(半径1000km)にいた生物は一瞬にして焼き尽くされました。
地殻の表層が気化して発生した巨大な熱波は、現在のカナダまで到達したと考えられています。
超巨大地震と大津波
衝突直後には、少なくともマグニチュード10.1という超巨大地震が発生し、地球全体を揺るがしました。
さらに、クレーターに海水が流れ込んだ反作用で逆流した水が巨大津波となり、地形によっては最大305メートルにも達し、世界中の沿岸部を壊滅させました。
「この世の終わり」の光景
衝突から約45分後、時速965キロの爆風が吹き抜け、赤熱したマイクロテクタイト(ガラス質の小球)が流星のように降り注ぎました。
空は暗さを増し、地表は灼熱の灰と岩屑に覆われる、まさに「この世の終わり」のような光景が地球に広がったと推測されます。
第3章:長期的な環境激変と「核の冬」
最終的に地球上の生命の大半(60%超)を消し去ったのは、衝突後のより長期的な環境への影響でした。
核の冬と食物連鎖の崩壊
衝突によって大気中に大量に巻き上げられた塵(ちり)や煤(すす)が地球全体を覆い尽くし、太陽光線を遮断しました。
この現象は核戦争後に予測される「核の冬」に極めて近い状態で、植物の光合成が劇的に減少し、食物連鎖の基盤が崩壊しました。
特に大量のエサを必要とする大型の恐竜は、この環境激変に適応できず、次々と絶滅していったと考えられています。
逆に、少ないエサで生き残れたネズミのような小型の哺乳類などが絶滅を免れました。
酸性雨とオゾン層の破壊
煤や灰が大気中から洗い流される過程で、酸性の泥のような雨が地球に降り注ぎ、生態系にさらなるダメージを与えました。
また、大規模な火事によって発生した毒素が、地球を保護するオゾン層を一時的に破壊したことも、絶滅に拍車をかけました。
第4章:絶滅の複合要因と最新研究成果
巨大隕石の衝突が主要因ですが、複合的な要因が絶滅に追い打ちをかけたと考えるのが合理的です。

絶滅に追い打ちをかけた複合要因説
火山活動の影響(デカントラップ)
現在のインドのデカン高原にあたる場所で、この頃に大規模な火山の大噴火活動(デカントラップ)があったこともわかっています。
この活動による環境変化が絶滅に追い打ちをかけたとする説も有力ですが、むしろこの活動によって放出された温室効果ガスが、「核の冬」の影響を緩和した可能性も指摘されています。
地層の元素パターンは、噴火由来の岩石よりも巨大隕石衝突と最もよく一致します。
隕石の起源判明(2024年)
2024年の最新研究では、チクシュルーブ隕石が木星より外側の「外太陽系」で形成された炭素質コンドライト隕石であったことが特定されました。
これは、地球に衝突する一般的な隕石とは異なる、太陽系の遠くからやってきた「不運な訪問者」によって、地球の歴史が大きく塗り替えられたことを示しています。
第5章:絶滅した種と生き残った種

絶滅した種と生き残った種
巨大隕石の出現により、1億5千万年にも及んだ恐竜史に終止符が打たれました。
絶滅した種
鳥類以外の恐竜のほか、アンモナイトや巨大な海生爬虫類(モササウルスなど)など、環境の変化に弱い大型の生物や食物連鎖の上位に位置する生物が壊滅的なダメージを受けました。
生き残った種
恐竜の1グループである鳥類(Avian Dinosaurs)は生き延び、今も繁栄を続けています。
現在の分類学では「鳥は恐竜そのもの」とされており、絶滅を語る際には「鳥類以外の恐竜が絶滅した」という表現がより正確です。
また、ネズミのような小型の哺乳類が、少ないエサで極限の環境を生き残り、後の哺乳類の時代への道を開きました。