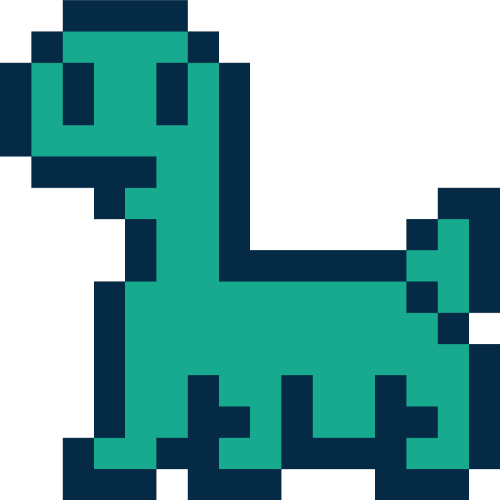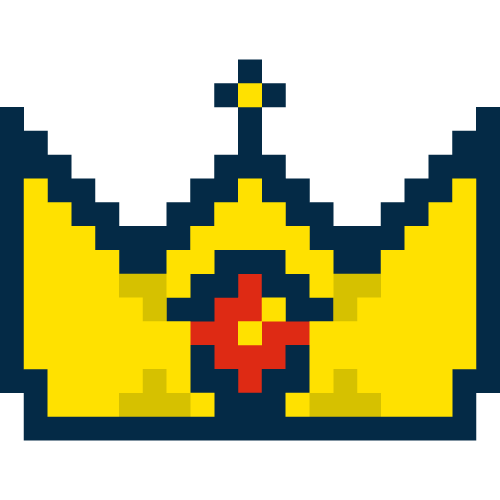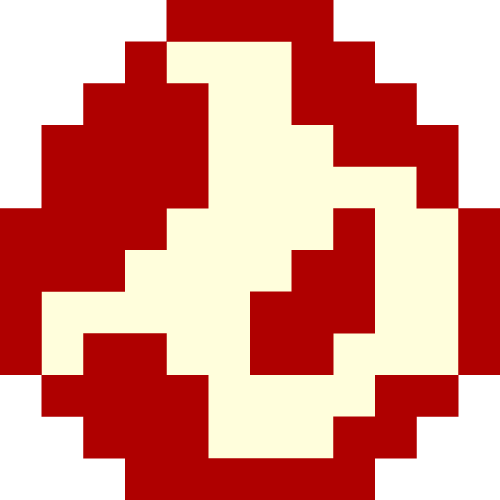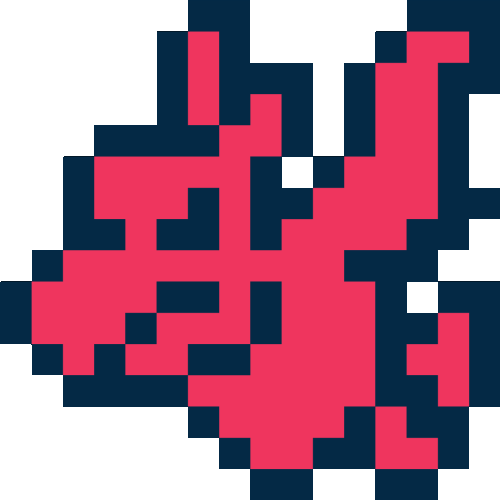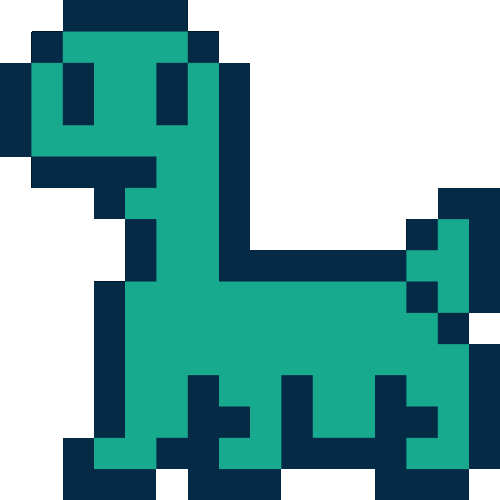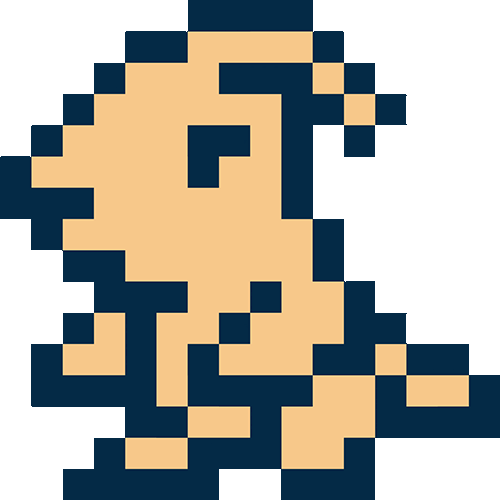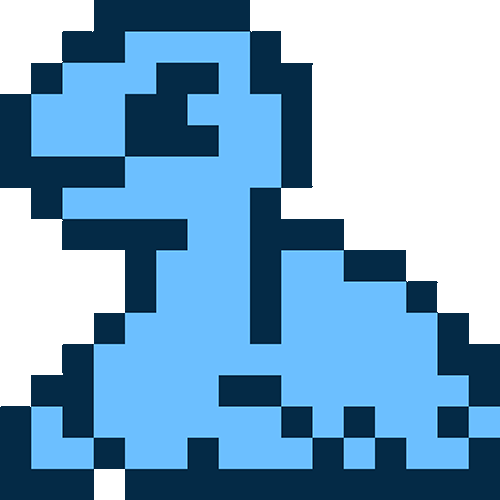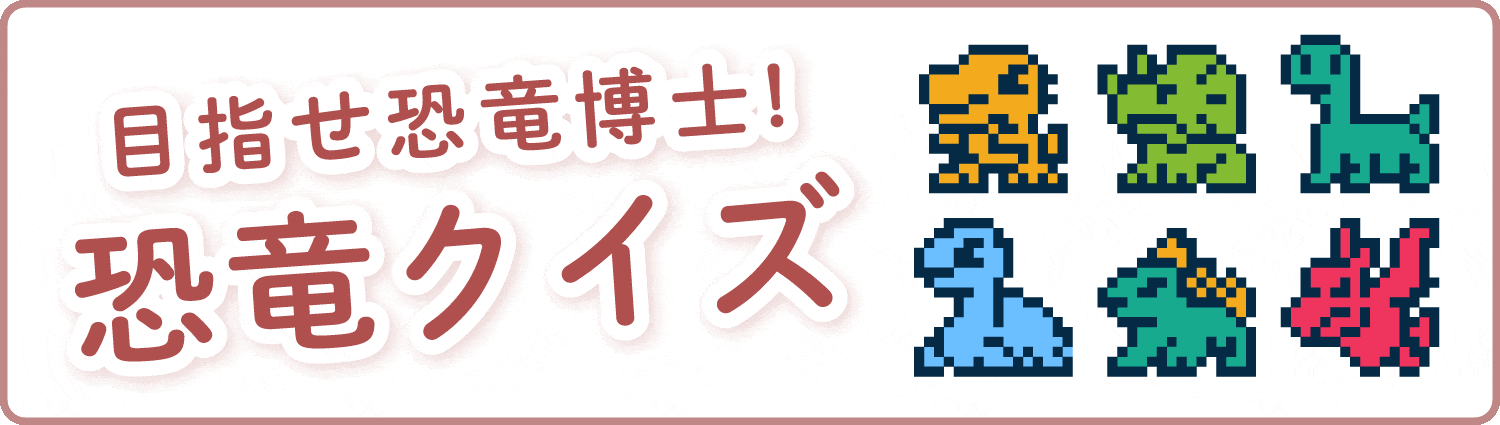恐竜とは何か?巨大爬虫類の進化、分類、そして驚異の生存戦略

恐竜とは、ギリシア語の deinos(恐ろしい)と sauros(トカゲ)に由来する名を持つ、中生代(三畳紀、ジュラ紀、白亜紀)に繁栄した爬虫類のグループです。
恐竜の仲間は今から約2億3千万年前の三畳紀に出現し、約1億6千万年もの長きにわたり地球を支配しました。
「恐竜」の学術的な定義と分類
恐竜は学術的に明確に定義されています。
現在の定義は、分岐分類学に基づき「鳥類(獣脚類)とトリケラトプス(周飾頭類)の直近の共通祖先と、そのすべての子孫」とされています。
この定義から、空を飛ぶ翼竜や海に住む首長竜、魚竜などは、共通祖先よりも以前に分化したため、恐竜には含まれません。
恐竜は、腰の骨である骨盤の形から、大きく2つのグループに分類されます。
表は横にスクロールできます
| 分類 | 骨盤の形 | 含まれる仲間 |
|---|---|---|
| 竜盤目 (Saurischia) | 恥骨が前下方を向き、トカゲの骨盤に似ている。 | 獣脚類(ティラノサウルスなど肉食恐竜)、竜脚類(ブラキオサウルスなど首長植物食恐竜) |
| 鳥盤目 (Ornithischia) | 恥骨が後ろに伸びて坐骨と平行になり、鳥類の骨盤に似ている。 | 鳥脚類(イグアノドンなど)、角竜類(トリケラトプスなど)、鎧竜類(アンキロサウルスなど) |
恐竜の成功を支えた特異な身体構造
恐竜が陸地で大成功を収めた最大の要因は、他の爬虫類にはない、効率的な身体構造を獲得したことにあります。
1. 直下型歩行(直立した脚)
恐竜を特徴づける最も重要な構造は、脚を身体の真下に伸ばす直下型歩行が可能であったことです。
効率的な移動
体重を支えるのに優れ、体を安定させて素早く動くことを可能にしました。

体を安定させて素早く動くことができた
呼吸の獲得
脚を横に伸ばす爬虫類と異なり、歩行中に身体をくねらせる必要がなく、歩行中も効率的に呼吸(酸素を取り入れる方法)を続けることができました。
この能力は、酸素濃度が低かった三畳紀後期において、恐竜が優位に立てた大きな要因の一つです。
2. 骨盤の特殊構造
恐竜の骨盤には穴(寛骨臼)が開いており、そこに大腿骨の先端がしっかりとはまり込むことで、直立姿勢を可能にしています。
この貫通した構造が、恐竜の素早さや、巨大な体を安定させることに役立っていました。
なお、四足歩行の竜脚形類や鳥盤類の多くは、もともと二足歩行が可能でしたが、巨大な体を支えるために、二次的に四足歩行に移行していったと考えられています。
恐竜の誕生と「鳥類」への進化
恐竜は、約3億年前に現れた有羊膜類(殻付きの卵を産む動物)の中でも、ワニや翼竜につながる主竜形類から、特有の直下型歩行という進化を獲得し、三畳紀に地球上に出現しました。
硬い殻で覆われた卵によって、乾燥した陸地でも繁殖できたことも、成功を後押ししました。

硬い殻で覆われた卵によって、乾燥した陸地でも繁殖できた。
恐竜は、爬虫類のように外の熱で体を温めるのではなく、自分で体を温める内温性の生き物だったと考えられています。
羽毛を備えた種もいたことから、彼らは哺乳類のように活動的な生活を送っていたとされます。

内温性の生き物だったと考えられている
恐竜は、約6,500万年前に起こった巨大隕石の衝突による大規模な絶滅イベントによって、鳥類以外の種が地球上から姿を消しました。

恐竜を絶滅に追い込んだといわれる「隕石衝突説」
しかし、現代の鳥類は、小型の獣脚類から進化したと考えられています。
現在の分類学では「鳥は恐竜(獣脚類)そのもの」とされており、私たちは今も、鳥という恐竜の子孫と共に生きているのです。

鳥類は小型の獣脚類から進化したと考えられている